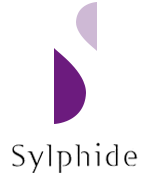着物ができるまで
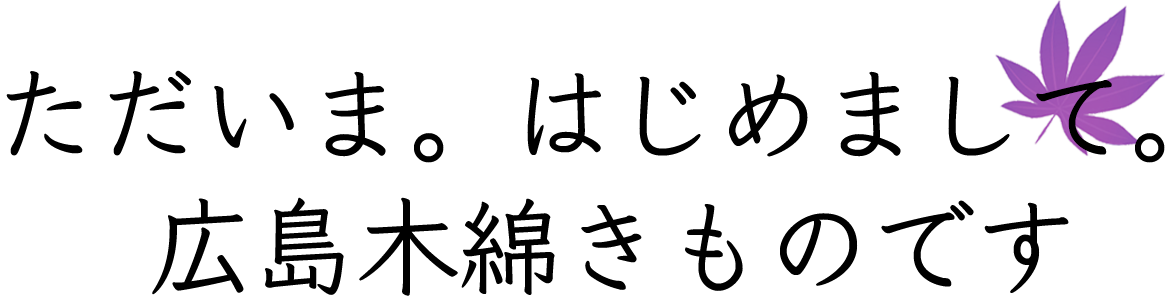
新しい、でも、とてもなつかしい。
そんな木綿きものを作りました。
着る人を包み込むような、ふわりと軽い肌ざわり。
化学染料を一使わない、自然の色。
人にも、地球にもやさしい、広島で生まれた木綿きものです。
あまり知られていませんが、広島は、
江戸時代のはじめから絶えることなく、木綿を織り続けて来た土地。
はじまりは、縞模様の木綿きもの。
幕末から昭和の半ばまでは、草花や動物、幾何学模様を織り出した“備後絣”で、
全国の人々に愛されました。
70年代、洋服中心の時代に入ると、いち早くデニムに取り組み、
現在では世界が認める高級デニムの産地に。
常に時代に合わせて変化を遂げてきました。
でも、今、原点回帰を――
シルフィードはそう考えます。
2020年代、人々が地球の悲鳴に立ち止まり、
おだやかで、無理のない歩幅へと、歩く速度を変え始めたこの時代に、
その歩みに寄り添うやさしいきものを作りたい。
広島を中心に、農家、そして職人を訪ね歩いて、
やがてそのきものは形をとり始めました。
新しい、広島木綿きものをご覧ください。
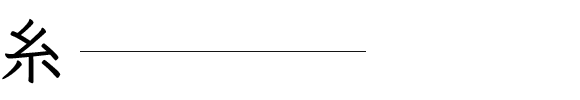
糸は、すべての始まりです。
新しい広島木綿の姿を思い描き始めた時、
シルフィードは、まず、糸にこだわりました。
択んだのは、高級シャツに使われる、張りのある木綿糸。
広島県福山市の「備後撚糸株式会社」で、
原料のコットンから丁寧に紡がれています。
この糸に対し、シルフィードは大きな決断をします。
それは、「糊付けをしない」ということ。
布を織るために織機(しょっき)という機械に掛ける時、
経糸(たていと)には強い力が加わります。
だから、途中で切れてしまわぬよう、糊でコーティングして強くする。
これが業界の常識です。
けれど、その分、織り上がった布は、
ごくわずかな硬さを帯びてしまいます。
シルフィードは、そのわずかなこわばりも
見逃したくはないと思いました。
究極にやさしい風合いの木綿布を作りたい。
だから、糊付けはしない。
自然のまま、生まれたまま。素直なやさしさをたたえた木綿糸なのです。

新しい広島木綿きものの最初の一枚は、藍色に。
はじめからそう決めていました。
その理由は単純です。
かつて、広島のきものは藍色だったから。
江戸時代なかばに始まった最初の縞模様のきものも、
そして、幕末からの備後絣も、その色は、藍色。
そう、瀬戸内の海のように深く、あたたかい、
ジャパンブルーと呼ばれるあの藍色です。
若き藍農家との出会いがありました。
福山市の山あいの村に、一面に広がる緑の藍畑。
夏、その葉を黙々と刈りとる藤井健太さんは、
もともとは同じ福山市の、もっとにぎやかな中心部の出身。
一度は福山を離れ、ビジネス界でキャリアを積んでいましたが、
ある日、たまたま参加したワークショップで、
藍に心を奪われ、やがて退職してしまいます。
江戸時代の藍作りを今も守る徳島県で、2年間の修業を積んだ後、独立しました。
どこで藍作りを始めるか?
日本中から候補地を探す中で、択んだのは、故郷福山の農地。
近くを大きな川が流れ、水が豊かで、藍の成長に欠かせない日照も十分。
周囲にはワインの原料となる葡萄畑が広がる滋味深い土地です。
屋号は「藍屋テロワール」。
ワインの世界で、葡萄が育った土地の風土を指す「テロワール」の語に、
広島の、この土地に根差していく覚悟が込められています。
藍は、春先に種を撒き、夏には腰の高さほどに育ちます。
ひと夏の間に2回から3回、葉を刈り、ビニールハウスに並べ、完全に乾燥させる。
秋を迎える頃、すっかり水気を失った葉は、濃い墨色へと変わっています。
まるでその内側にブルーの色を深くかくすように。
そして、10月の半ば、黒く乾いた藍の葉を、
畑の脇の小屋に敷き詰めていきます。
土間いっぱいに敷き詰めたら、その上に二層目を。三層目を。四層目も。
次々と重ねて最後にはちょっとした小山ほどになった葉に、
少量の水を打ち、藁のむしろをかぶせて寝かせる――
最も神秘的な工程、発酵の始まりです。
10月から始めて、翌年の2月まで、18週間。
週に1回、藤井さんは小屋に入り、藍の山をかき混ぜます。
これは、藍を酸素に触れさせるため。
そして水を打ち、またむしろをかけて寝かせる。
“切り返し”と呼ばれるこの工程を繰り返すうちに
いつしか藍は生き物のように熱を持ち、
鼻をつくすっぱい匂いが小屋いっぱいに広がっていきます。
染色は、化学だと言われます。
けれどこれは一切合成物質を使わない化学実験。
水と空気だけの、100パーセントの自然発酵です。
そして、年を越えた2月、藍の葉はもう葉ではありません。
蒅(すくも)と呼ばれる染料へと熟成しています。
ここから、藤井さんは紺屋(こうや)へと変わります。
紺屋とは、江戸時代、糸や布を染める職人を呼んだ名前。
藍屋テロワールは藍農家であり、紺屋でもある。
そんな稀有な存在なのです。
染めの作業を行うのは、畑の脇のもう一つの小屋。
真ん中に、子ども用プールほどの巨大な釜。
その中に、まずは、蒅(すくも)。
そして、灰汁(あく)、貝灰、ふすま。
どれも自然の素材である三つの媒染剤を入れ、湯で溶かします。
でも、すぐに染められるわけではありません。
自然のことは、何でも、ゆっくりと。
数日かけて調整しながら染液を作ります。
意外なのは、出来上がった染液が、
ブルーではなく茶色がかった墨色であること。
そう、ブルーはまだかくれんぼを続けているのです。
いよいよ備後撚糸***番糸を漬け込んでいく準備が整いました。
糸は、はじめは黄緑色に染まります。
数回、じっくりと綛を回して、
奥深くまで染み通るように。それでもまだ糸は黄緑色のまま。
最後までかくれんぼが続きます。
やがて、天日に干してから、数分後。
ついに待ち望んだ色が現われてきました。
ジャパンブルー、
一年をかけて手に入れたこの色。
発酵も、媒染剤も、すべて自然の素材だけを使った、
やさしく、深い青です。
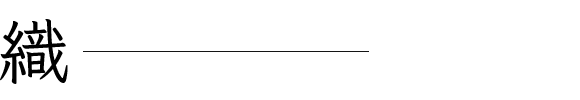

工場のあちこちから、
カシャン、カシャン、カシャンという音が和音になって聞こえてきました。
いよいよ最終工程、織りの始まり。
カシャン、カシャンは、カシャ、カシャ、カシャと忙しいものから、
カシャーン、カシャーン、カシャーンとのんびりした音まで。
ずらりと並んだ“織機(しょっき)”が、一目ずつ、
経糸(たていと)に緯糸(よこいと)を通して押さえ込み、
一枚へと織り上げていく――そんな、布の命の始まりの音です。
福山市の中村金襴工場は、業界に名をとどろかす凄腕の製織工場。
ラグジュアリーな絹の帯地からカジュアルなデニムまで、織れないものはないことで知られています。
新しい広島木綿きものは、どうしても中村金襴で織りたい。
そう決めていました。
木綿の布は、もともと、きりりと・しゃきっとしがちなもの。
その木綿を、ふっくらと空気を含んで、
あたたかくやさしく仕上げてみたい。
それに糊付けをしていない今回の糸は、
織機にかけた時に切れやすい。
どんな布でも織ってしまう中村金襴なら、
こんな難題だらけの布も相談を持ちかけてみたのです。

工場にずらりと並ぶ70台の織機の、右側の端っこ。
そこに、特別な1台があります。
一般的な木綿用の織機に、中村金襴のこだわり屋の社長が改造を重ね、
もはやオリジナル機械になった改造織機。
この織機で、広島木綿は織られています。
常に一人、技術者がついているのは、
経糸と緯糸の調子を細かく整えるため。
そう、糊付けをしない広島木綿の糸は、
織機にかけると切れやすい。
だから、常に人の眼の見守りが必要なのです。
カシャン、カシャンではなく、
カシャーン、カシャーンと、ゆっくりと。
時に止まって、また、カシャーン、カシャーンが始まる。
ゆっくりと、じっくりと打ち込まれ、命が吹き込まれていきます。

やさしい糸、やさしいブルー。そしてやさしく織り込んでいくこと。
新しい広島木綿は、たくさんのやさしいと、たくさんのゆっくりから生まれた、
ふわりとやさしいきものです。
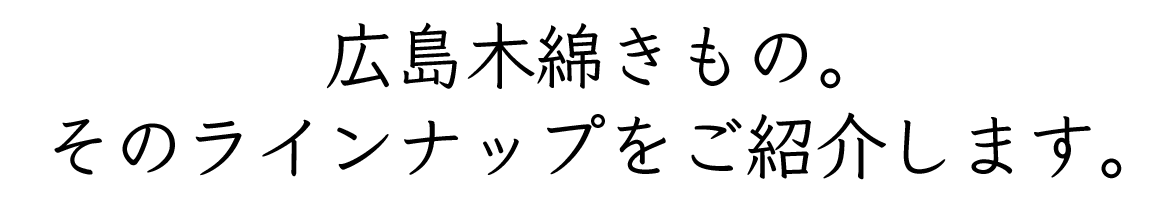
| 広島木綿きもの genuine | 広島で撚った木綿糸と、広島で育った藍で染めた、 地球にやさしい、そして、 100パーセント・メイドイン広島の反物です |
| 広島木綿きもの・たわん | 「たわん」とは、広島弁で、少し背が届かないこと。 その言葉のように、少しだけ作り方を変えることで、価格をおさえた反物です。もちろん、genuineのやさしさはそのままに。 変えたこと。その第一は、緯糸(よこいと)にインド綿糸を使ったこと。 そして第二は、インド藍で染めたこと。 とは言え、それは、オーガニック認証取得の素性正しいインド藍。 そして、染める場所は、インドではなく広島。 備後撚糸の工場で、ゆっくり丁寧に染めた糸は、織り上がるとやっぱりやさしい色をしています。 |
| 絹糸マリアージュ | 経糸(たていと)には、藍屋テロワールで染めた木綿糸、緯糸(よこいと)には絹の紬糸を。 絹が放つかすかな光沢と、紬糸ならでは、 ところどころに顔を出す小さな丸いふしがアクセントに。 |

自然の優しい色を求めて、広島木綿きものは、
広島の外へも飛び出していきます。
最初に向かったのは、大分。
温暖な大地にすくすくと育つびわの畑へ。
その葉を煮出して生まれる染料に漬け込むと、
糸は、甘い甘いびわの実のような、
やさしいベージュに染まりました。
そして、奄美大島へも。
この島では、独特の粘り気ある土による泥染めが、
幕末から行われています。
命を育む大地が授けてくれるのは、
厳しさをたたえた、灰色がかった茶褐色。
その凛とした強さに拮抗する絞り染めをほどこしました。